


ブログ
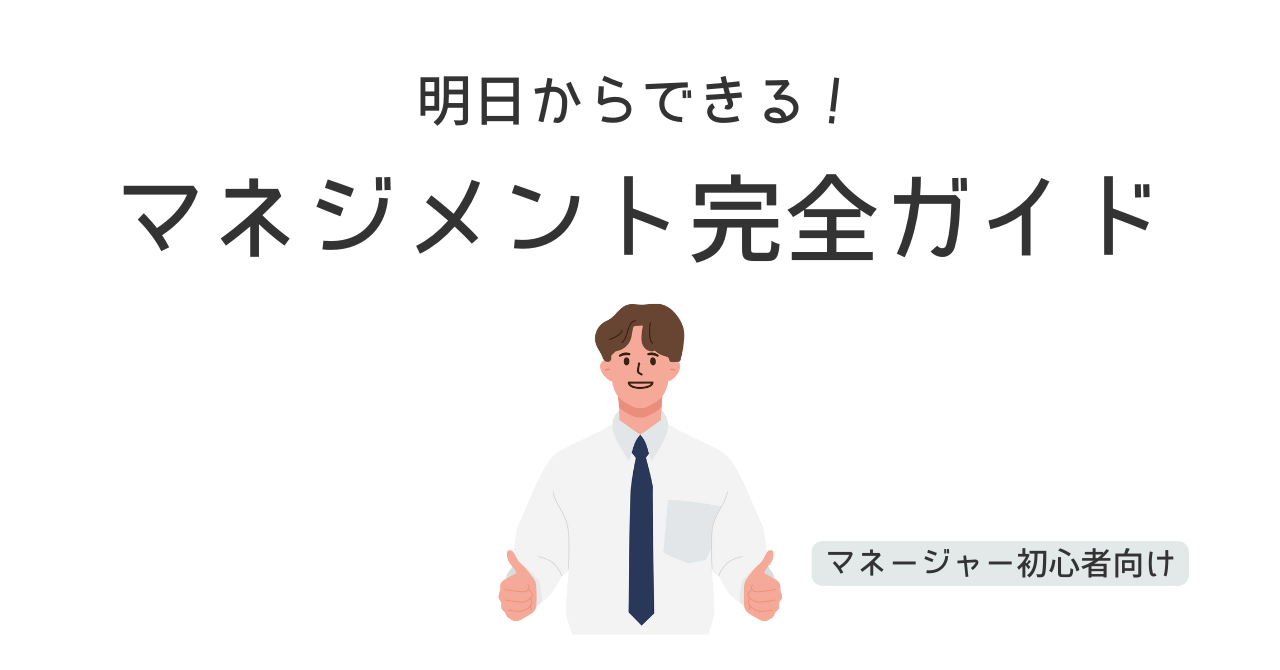
初めてマネージャーになったものの、「何から手をつければいいのか分からない」「チームがうまく機能しない」「メンバーのモチベーションが上がらない」といった悩みを抱えていませんか?
私も長年、BtoB企業の営業組織を見てきましたが、特にスタートアップでは、マネジメントを体系的に学ぶ機会がないまま、突然マネージャーになるケースが少なくありません。その結果、属人的なマネジメントに陥り、チームの成長が停滞してしまうことも。
そこで今回は、株式会社ナレッジワーク代表の麻野耕司さんが提唱する「4つのマネジメント」フレームワークを、実践的な視点から解説します。麻野さんは『THE TEAM 5つの法則』の著者としても知られ、多くの成長企業の組織変革を支援してきた方です。
本記事では、各領域の定義から実践方法まで、具体例を交えながら詳しく解説していきます。
目次
1.フィロソフィー・マネジメント 〜チームの「魂」を育てる〜
なぜフィロソフィーが重要なのか
フィロソフィー・マネジメントとは、企業のミッション・ビジョン・バリューといった「理念」をチームに浸透させ、メンバー全員が同じ方向を向いて進めるようにするマネジメントです。
麻野さんは「最初に取り組んだのが企業理念の策定だった」と述べているように、これはすべてのマネジメント活動の土台となります。なぜなら、共通の目的意識がなければ、どんなに優秀な人材を集めても、バラバラの方向を向いてしまうからです。
理念浸透の4つのステップ
理念の浸透は、一朝一夕には実現しません。以下の4つの段階を意識的に進める必要があります。
- 認知:まず、メンバーが理念の存在と内容を知る
- 理解:理念が自分の仕事にどう関係するかを理解する
- 共感:理念に対して感情的なつながりを感じる
- 実践:日々の業務で理念に基づいた行動をとる
実践例 〜ナレッジワークの取り組み〜
麻野さんが創業したナレッジワークでは、「LIFE WITH ENABLEMENT(できる喜びが巡る日々を届ける)」というミッションを掲げ、初期メンバー集めの段階から、このミッションに共感する人材を採用しています。
また、ディズニーの例も参考になります。多くの従業員は給与や職種よりも「夢の国を創る」「ハピネスを届ける」といった理念に惹かれて働いており、これが強い組織文化を生み出しているのです。
今すぐできるアクションプラン
- チームの存在意義を言語化する
- 「私たちは何のためにこの仕事をしているのか?」に答える明確なフレーズを作る
- メンバーと一緒にワークショップを開き、共創プロセスを経る
- コアバリューを3〜5個設定する
- 日々の業務で大切にすべき行動指針を具体的に定める
- 「この価値観を体現する行動」と「反する行動」をリストアップ
- 理念を日常に埋め込む
- 朝会や定例会で理念に紐づく成功事例を共有
- 評価制度に理念の実践度を組み込む
- マネージャー自身が理念を体現する行動を示す
2.ストラテジー・マネジメント 〜勝つための道筋を描く〜
戦略なきチームの末路
ストラテジー・マネジメントとは、チームや事業の「何をするか」を明確にし、限られたリソースを最も効果的に配分するためのマネジメントです。
麻野さんは「顧客がなぜ自社の商品を選んでくれるかの理由を作ることだ」と述べていますが、この「選ばれる理由」こそが戦略の核心です。明確な戦略がなければ、努力のベクトルが定まらず、「あれもこれも」と手を広げた結果、どれも中途半端になってしまいます。
戦略策定のための分析フレームワーク
3C分析で環境を理解する
- Customer(顧客):誰が私たちのサービスを必要としているか?
- Competitor(競合):同じ市場で戦っている相手は誰か?
- Company(自社):私たちの独自の強みは何か?
SWOT分析で現状を整理する
| 内部環境 | 外部環境 |
|---|---|
| 強み(Strengths) ・技術力の高さ・顧客との信頼関係 | 機会(Opportunities) ・市場の成長・規制緩和 |
| 弱み(Weaknesses) ・営業力不足・資金力の限界 | 脅威(Threats) ・新規参入の増加・技術の陳腐化 |
クロスSWOT分析で戦略を導出する
単に要素を洗い出すだけでなく、それらを掛け合わせて具体的な戦略を生み出します。
- S×O戦略(積極化):強みを活かして機会を最大限に活用
- W×O戦略(段階的強化):機会を利用して弱みを克服
- S×T戦略(差別化):強みを使って脅威を回避
- W×T戦略(防衛/撤退):最悪の事態を避ける対策
実践例 〜カスタマーサポートチームの変革〜
あるSaaS企業のサポートチームは、「問い合わせ対応件数」というKPIに追われて疲弊していました。マネージャーが3C分析を実施した結果、以下のことが判明しました。
- 顧客は迅速な回答だけでなく、問題の再発防止を望んでいる
- 競合も同様に件数主義で差別化できていない
- 自社の強みは製品知識豊富なベテランスタッフの存在
そこで、チームのKSF(重要成功要因)を「問い合わせ件数の処理」から「問い合わせ発生率の低減」へと転換。ベテランスタッフが中心となってFAQやチュートリアル動画を作成し、「火消し部隊」から「価値創造部隊」へと変貌を遂げました。
戦略マネジメントの実践ステップ
- 顧客価値の明確化
- 「○○な問題を、△△な方法で解決する」という形で一文にまとめる
- ターゲットと市場ポジションの設定
- リソースが限られるスタートアップだからこそ、戦う土俵を選ぶ
- 業務プロセスの再設計
- 戦略に合わせて社内の業務フローや役割分担を見直す
- 戦略の共有と対話
- 単なる上意下達ではなく、背景や狙いを理解してもらう
- 定期的な戦略レビュー
- 四半期ごとに環境変化を踏まえて戦略を見直す
3.パフォーマンス・マネジメント 〜成果を生み出す仕組みづくり〜
PDCAサイクル、本当に回せていますか?
パフォーマンス・マネジメントとは、チームや個人の目標を設定し、その進捗・成果を管理することで、継続的に成果を創出する仕組みです。
多くのチームがPDCAサイクルを「知っている」と言いますが、実際には形骸化しているケースが少なくありません。麻野さんも「設定した目標とその施策に対する検証と改善が行われないままだと、問題点が放置され効果が低下する」と警鐘を鳴らしています。
PDCAサイクルの正しい回し方
| フェーズ | やるべきこと | よくある失敗 |
|---|---|---|
| Plan(計画) | ・SMARTな目標設定 ・5W2Hで具体的な行動計画 ・成功の測定基準(KPI)を定義 | ・曖昧な目標設定 ・過去の踏襲で仮説がない ・すぐ実行に移る |
| Do(実行) | ・計画に沿って実行 ・内容、日時、結果を記録 ・計画外の事実も記録 | ・記録を残さない ・途中で勝手に変更 ・完璧主義で遅れる |
| Check(評価) | ・データに基づく客観的評価 ・目標達成/未達成の要因分析 ・成功要因と失敗要因の特定 | ・感覚で評価する ・責任追及に終始 ・評価を省略する |
| Action(改善) | ・成功要因の標準化 ・失敗要因への改善策立案 ・次の計画への反映 | ・精神論に終わる ・対症療法に留まる ・改善策を反映しない |
KPIとOKR:目的に応じた使い分け
KPI(Key Performance Indicator)
- 100%達成が基本
- 定常業務の効率化やプロジェクト進捗管理に適している
- 人事評価と連動することが多い
OKR(Objectives and Key Results)
- 60〜70%達成でも成功
- 野心的な目標でチームの創造性を引き出す
- 通常は人事評価と切り離す
実践例 〜OKRで挑戦的な文化を作る〜
Googleをはじめ多くの先進企業が採用するOKRは、以下のような構造になっています。
Objective(目標):顧客体験を劇的に改善する
Key Results(主要な結果):
- NPS(顧客推奨度)を30から50に向上させる
- カスタマーサポートの初回解決率を70%から90%に改善
- 新機能のアクティブ利用率を50%達成
データドリブンな進捗管理の実装
- KPIツリーの作成
- 会社のKGI(最終目標)から部門KPI、個人KPIへとブレークダウン
- メンバーが自分の仕事の意味を理解できる
- ダッシュボードの構築
- 進捗を誰でも確認できる「見える化」
- リアルタイムでの状況把握
- 定例レビュー会議の設計
- 週次:進捗確認と障害の早期発見
- 月次:トレンド分析と軌道修正
- 四半期:大きな振り返りと戦略見直し
4.ピープル・マネジメント 〜人の可能性を最大化する〜
なぜピープル・マネジメントが最重要なのか
ピープル・マネジメントとは、メンバー一人ひとりの力を最大限発揮させるためのマネジメントです。麻野さんは「従業員のエンゲージメント(仕事への情熱や会社への愛着)を高めることを重視する」と述べています。
実際、人材こそがスタートアップ最大の資産です。優れた理念も巧みな戦略も、それを実行する「人」なくして実現しません。また、優秀な人材ほど転職の選択肢が多い今、エンゲージメントの高い職場環境を作ることが、採用競争力にも直結します。
1on1ミーティングについて
日本でもヤフーが全社導入したことで注目された1on1は、今やパナソニック、日清食品、ソニー、楽天など多くの企業が取り入れています。
効果的な1on1の進め方
- 目的の明確化
- 「この時間は君の成長のための時間」と伝える
- 進捗確認の場ではないことを強調
- アジェンダの共創
- 部下にも話したいテーマを準備してもらう
- 主体性を引き出す
- 幅広いテーマ設定
- 業務の課題だけでなく、キャリアビジョンや人間関係も扱う
- 時にはプライベートな話題も
- 傾聴とパワフルな質問
- 話を遮らず、相槌で関心を示す
- 「なぜそう思うのですか?」「制約がなければどうしますか?」
GROWモデルによるコーチングの実践
GROWモデルは、部下が自ら答えを見つけ出すプロセスを支援する強力なフレームワークです。
| ステップ | 目的 | 質問例 |
|---|---|---|
| G – Goal(目標) | 本人が望む理想状態を明確化 | 「この面談が終わった時、何が明確になっていたら理想的?」 |
| R – Reality(現状) | 目標に対する現在地を把握 | 「その目標を10点満点とすると、今は何点?」 |
| O – Options(選択肢) | 可能な行動の選択肢を拡大 | 「制約がなかったら、どんなことができる?」 |
| W – Will(意志) | 具体的な最初の一歩を決定 | 「明日からすぐに始められることは何?」 |
心理的安全性の高いチーム作り
Googleの調査プロジェクト「アリストテレス」が明らかにしたように、心理的安全性はチームの成功を予測する最も重要な因子です。
心理的安全性を高める具体的な行動
- 率先して弱みを見せる
- 「実は私も○○が苦手で…」と自己開示
- 失敗を学習機会として扱う
- 「なぜうまくいかなかったか一緒に考えよう」
- すべての質問を歓迎する
- 「いい質問だね」と肯定的に受け止める
- 健全な対立を促進する
- アイデアへの批判はOK、人格攻撃はNG
エンゲージメント向上に繋がる施策
- 成長機会の提供
- 小さなプロジェクトリーダーを任せる
- 社外研修や勉強会への参加支援
- 個人の強みに合わせた役割設計
- 分析が得意な人にデータ関連タスク
- 顧客志向の強い人にユーザーインタビュー
- 認知と称賛の文化
- 日常的な「ありがとう」の習慣化
- ピアボーナス制度の導入
- キャリア支援
- 個人のキャリア目標と会社目標のすり合わせ
- メンター制度の活用
5.4つのマネジメントを実装するロードマップ
マネジメント・コンパスで全体像を把握する
4つのマネジメントは独立したものではなく、相互に影響し合うシステムです。
- フィロソフィー(なぜ)→ すべての活動の原点
- ストラテジー(何を)→ フィロソフィーに基づく方向性
- パフォーマンス(どうやって)→ ストラテジーを実行に移す仕組み
- ピープル(誰が)→ システム全体を動かす原動力
ケーススタディ:低迷チームの立て直し
状況:開発チームで納期遅延が常態化し、メンバーの表情は暗く、会議での発言も少ない。
4つの観点からの診断
- フィロソフィー:仕事の意義を見失っている
- ストラテジー:優先順位が不明確
- パフォーマンス:技術的負債による非効率
- ピープル:心理的安全性の欠如
解決アプローチ
- 全メンバーと1on1を実施(ピープル)
- 顧客を招いて製品への感謝を直接聞く機会を設定(フィロソフィー)
- 製品バックログを見直し、顧客価値の高い機能に絞り込む(ストラテジー)
- 技術的負債返済の時間をスプリント計画に組み込む(パフォーマンス)
段階的実装のすすめ
すべてを一度に変えようとすると失敗します。以下のステップで段階的に進めましょう。
Phase 1(1〜2ヶ月目):現状把握と関係構築
- 各メンバーと1on1を開始
- チームの強み・弱みを分析
- 小さな成功体験を作る
Phase 2(3〜4ヶ月目):基盤づくり
- チームのミッション・バリューを共創
- 基本的なKPIを設定
- 定例レビュー会議を開始
Phase 3(5〜6ヶ月目):本格展開
- 戦略の見直しと共有
- OKRの導入検討
- コーチング型マネジメントの実践
Phase 4(7ヶ月目以降):継続的改善
- PDCAサイクルの定着
- 他チームへの横展開
- 次世代リーダーの育成
6.4つのマネジメント手法まとめ
ここまで、麻野耕司さんの「4つのマネジメント」フレームワークを詳しく見てきました。最後に、各領域の要点をもう一度整理しておきます。
| マネジメント領域 | 問い | キーアクション |
|---|---|---|
| フィロソフィー | なぜ存在するのか? | ミッション・バリューの共創と浸透 |
| ストラテジー | 何をすべきか? | 3C/SWOT分析による戦略策定 |
| パフォーマンス | どう実行するか? | PDCAサイクルとKPI管理 |
| ピープル | 誰と共に歩むか? | 1on1とコーチングによる成長支援 |
今すぐ取り組める3つのアクション
- 今週中に全メンバーと15分の1on1を設定する
- まずは「最近どう?」から始める
- 傾聴に徹し、信頼関係を築く
- チームミーティングで「私たちは何のために働いているか」を議論する
- 30分の時間を確保
- メンバーの意見を引き出す
- 一つだけ測定可能な目標(KPI)を設定する
- シンプルで分かりやすいものから
- 週次で進捗を確認する習慣を作る
マネジメントに「正解」はありません。しかし、体系的なフレームワークを持つことで、より良いマネジメントの実践は必ず可能です。
4つのマネジメントは、スタートアップという不確実性の高い環境で、チームの力を最大限に引き出すための羅針盤です。完璧を目指す必要はありません。小さく始めて、継続的に改善していくことが何より大切です。
※本記事は麻野耕司さんの著書やブログ、SNSを調査して、私の知見を元に独自解説しました
参考情報:
PDCAマネジメントのコツ|メンバーマネジメントのコツも解説
Management Boot Campのお知らせ
筆者:中元鈴香
BtoB領域に特化したライター。5年以上にわたり、SaaS、IT、人材、コンサル業界のコンテンツ設計とライティングに従事。上場企業のオウンドメディア立ち上げや、中小企業のSEO内製化支援も多数経験。

